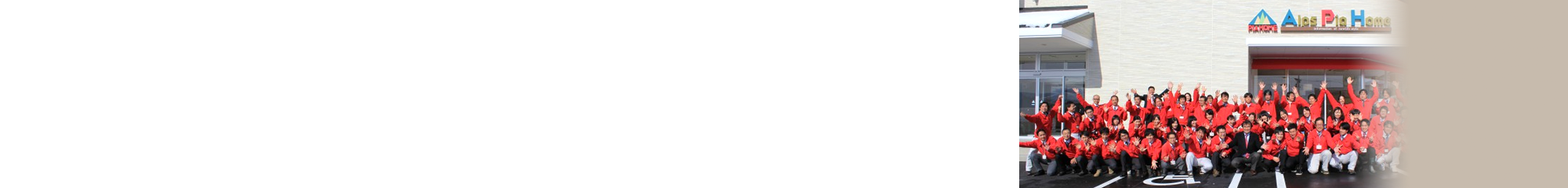みなさん、こんにちは!
上田店の栁沢です。
今回のブログは私の故郷、長和町のお祭りについてお伝えします。
「おたや祭り」というお祭りです。
毎年1月14日、15日に開催されるお祭りです。

古町豊受大神宮
このお祭りは、長和町古町の豊受大神宮の例大祭で、通称おたや祭りとして知られています。
このお祭りの特色としては、町内5カ所で山車(だし)飾りが奉納されている事です。
ここで飾られる山車は一般的な引き歩く屋台式の山車ではなく、固定して飾られることが特徴で、素朴な農民芸術であり民衆芸能として伝承されています。
この山車は、長野県の無形民俗文化財にも指定されています。
最も古い記録としては、江戸時代の後期の文政6年(1828年)の文書に確認されているとの事ですので、今から197年前、もしくはそれ以前から続いている伝統あるお祭りのようです。
「おたや」の名の由来は、新しく水田を開くために建てられた田小屋を指す「田屋」とも、また大麻(たいま)(神札)や暦を配ったり布教に巡回する御師(おし)の宿泊所「旅屋(たや)」ともいわれる。
この旅屋が時とともに神聖視されるようになり、やがて旅屋のある伊勢社の祭りを「おたや祭り」と呼ぶようになったとする説があります。
山車づくりに参加するのは、区会単位で構成する上町、上中町、中町、下町・藤見町、桜町の各保存会によって製作されています。
山車の題材は区会単位で決められる。歴史上の物語や日本のおとぎ話の名場面、また、干支にちなんだものなどが選ばれていて、素朴さのなかに風雅が漂う造形を作りあげていくものとなっています。

上宿 第1場(文福茶釜 綱渡りの場)

上中町 第2場(道成寺 大蛇になった乙女の場)

中町 第3場(九尾の狐(玉藻前)伝説の場)

下町・藤見町 第4場(忠臣蔵 討ち入りの場)

桜町 第5場(信濃路をいく黄門一行の場)
今年も歴史ある古町豊受大神宮を参拝して、今年一年の無病息災、平穏無事をお願いして参りました。
仕事の更なる発展と、家族全員皆元気で健康で過ごせるように!
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
それでは、また!
以上、上田店の栁沢でした。